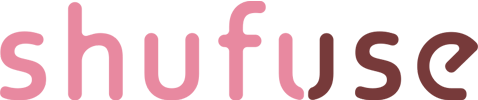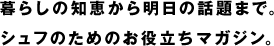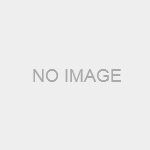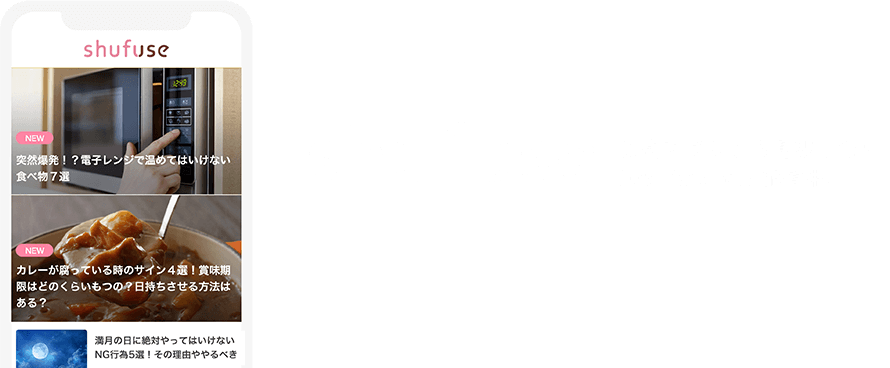目次
梅雨の時期に起こりやすいトラブル6選!
1.カビ

梅雨といえばジメジメしてカビが気になる季節です。カビは気温25~30℃、湿度70%以上でどんどん繁殖していきます。日本の平均的湿度は6月になると78%、8月は80%近くまで上がるそうです。
カビは見た目の不快さだけでなく、カビが繁殖した場所に長時間いると、胞子を吸い込むことになります。そのことがアレルギーぜん息を引き起こす原因となったり、真菌症という病気を発症してしまうこともあるようです。
2.害虫
湿度が高くなると特定の害虫には過ごしやすい環境が整います。特に繁殖するのは「ダニ」や「コバエ」です。気密性が高くなるとダニはより発生しやすいので、風通しをよくするよう心がけてください。
コバエは生ごみや排水口の近くですぐに発生しますので、生ごみはこまめに捨て、排水口は清潔を保ちましょう。また、戸建ての屋外では「ヤスデ」や「ムカデ」に注意です。対策として落ち葉や廃材をそのまま置いておくのは避けたほうがよいでしょう。
3.結露

結露というと冬に窓ガラスを濡らすものが一般的ですが、梅雨の時期にも「夏型結露」というものがあるそうです。梅雨の時期は気温が高めですが、湿度で水分量が多すぎて空気中の水分が飽和状態になると言われています。
冬の結露と違い、家の中でも目につきにくい壁の裏や床下、押し入れの中などでも発生することもあるとのことです。そのままにしておくとカビの発生も招くので、梅雨の時期の結露にも注意が必要です。
4.食中毒
ジメジメが続く梅雨の時期は、食中毒菌の繁殖も活発になる時期で、気温が高い夏の時期まで続きます。特に肉や魚には原因となる菌やウィルスがいることを前提として考えて、取り扱いに気を付けたほうが良いでしょう。
買い物の時には生鮮食品を持ち歩く時間を減らしたり、氷や保冷剤を活用します。また、要冷蔵の物は常温で置きっぱなしにしないよう気を付けて下さい。
5.体調不良

梅雨の時期は晴れていて気温が高くなったり、雨で肌寒い日があったりと寒暖差が激しいことがあります。寒暖差が大きいことで体がストレスを感じたり、疲れやすくなると言われています。
また、低気圧や雨の日が続くと明るい日の光に当たらなくなります。そのことで副交感神経が優位になり、だるさやめまい、頭痛、吐き気、食欲不振などをまねくことがあるそうです。
規則正しい生活と良質な睡眠、疲労回復効果やストレス対策に効果的なビタミンB・C群の摂取など心がけましょう。
6.肌トラブル
蒸し暑い梅雨の時期は汗をかくことも増え、テカリや吹き出物ができたり、メイクも崩れやすくなるなど肌トラブルも絶えない季節です。ジメジメしていても、エアコンや除湿器によって肌は乾燥しがちです。
さらに、くもり空でも紫外線は降り注いでいるため、紫外線対策を怠ると紫外線により肌の水分が蒸発して、潤いが保てなくなると言われています。梅雨の時期でもUVケアや保湿対策はしっかり行い、汗は放置せずこまめにふき取るようにしましょう。
湿気を取り除く方法

こまめに換気をする
湿気を溜めないように逃げ場を作るようにします。できたら複数個所の窓を開けて空気の通り道を作りましょう。雨の日も室内に雨が入り込むような強い雨風でなければ、こまめに窓を開けたほうが良いそうです。
また、キッチン、シンク下、押し入れ、クローゼットの扉などもこまめに開放します。汗を吸い取っている布団は湿気を帯びたまましまい込むのを避けましょう。定期的に干したり布団乾燥機を使いできるけ除湿してからしまいます。
除湿剤の設置
シューズボックスやクローゼット、シンク下には設置するだけで効果のある除湿剤を活用しましょう。市販の除湿剤も手軽ですが「重曹」を使った湿気対策もおすすめです。特に広い空間の除湿には口が大き目の容器に重曹を入れ、ガーゼと輪ゴムで蓋をしておいておくのが良いそうです。
湿気を吸うと重曹が固まってくるので、交換時期となります。固まった重曹は掃除や洗濯に再利用できます。
さいごに

梅雨の時期はカビの繁殖以外にも、さまざまなトラブルが発生するのですね。除湿器の利用も効果的ですが、種類によっては使用時の音が気になったり、室温が上がったりなど使いにくい点もあります。
湿気対策機能のあるカーテンなどもあるようなので、湿度対策をしっかり行いたい場合は機能的なカーテンを利用するのも良いかもしれません。