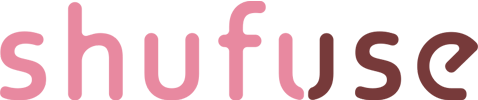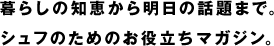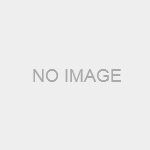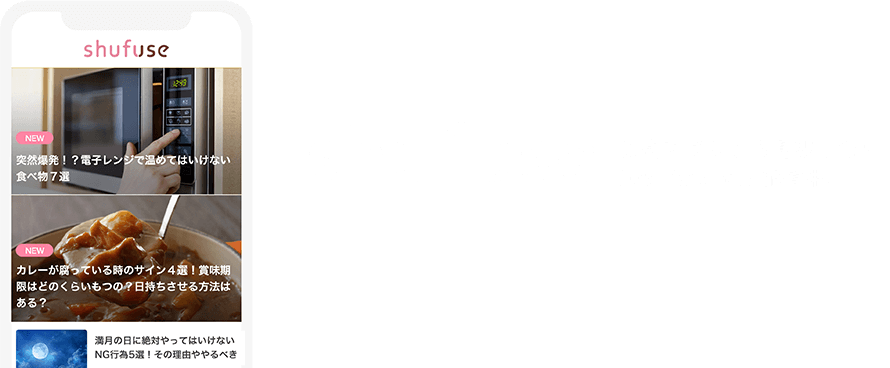目次
換気扇は掃除しないと換気効果が低下してしまう

皆さんは換気扇をどのくらいの頻度で掃除していますか。一般的に、換気扇は頻繁に掃除する必要はないと言われていますが、全く掃除していないと多くの汚れが蓄積され、換気効果が低下してしまいます。
理想は半年に1回を目安にフィルター、ファンまでを掃除することが推奨されているので、ぜひ換気扇をあまり掃除していないという方は、半年に1回を目安に掃除するよう心がけてください。
要注意!換気扇が壊れてしまう『絶対NG行為』5選

最近では換気扇掃除に便利なグッズも多く販売されています。しかし、換気扇は電気機器なので、慎重に扱わなければいけません。ここでは換気扇が壊れてしまう絶対NG行為を紹介するので、掃除の際は十分注意してください。
1.直接換気扇にスプレーを吹きかける
最近では、換気扇掃除グッズとしてスプレータイプの商品が多く販売されています。しかし、直接換気扇にスプレーを吹きかける行為は控えてください。
直接換気扇にスプレーを噴射してしまうと、噴射された液体が目的のフィルターやファンだけでなく、その周りに付属している電気機器にもかかってしまう恐れがあります。
電気機器はとてもデリケートな部品なので、液体がかかってしまうと故障の原因となります。換気扇掃除をする際は、あらかじめゴム手袋をして部品を取り外し、シンクや調理台の上などを利用して掃除を開始しましょう。
2.アルカリ性液体洗剤を使って掃除する

換気扇に重曹やキッチン掃除用のアルカリ性洗剤を使用するという方もいますが、レンジフードの説明書を確認すると、アルカリ性洗剤ではなく中性洗剤を推奨しているメーカーが多いです。
最近の中性洗剤は油汚れに効くものも多いですし、アルカリ性洗剤をファンなどに使用してしまうと、塗装やコーティングを剥がしてしまう恐れがあるからです。
せっかく特殊加工されているファンにアルカリ性洗剤を使用して、加工を剥がしてしまうと、より汚れがこびりつきやすくなります。もしもアルカリ性洗剤を使用する場合は、必ず換気扇用の洗剤を使用するようにしてください。
3.掃除や点検のために自分で換気扇を分解する
一般的に、私たちが自分で換気扇を掃除する際は、フィルター、もしくはファンまでが限界です。その奥の本体までを掃除したり点検したりするため、分解しようとすると、感電や換気扇の故障といったトラブルを引き起こす恐れがあります。
換気扇に限らず、電気機器の分解を素人が行うのは非常に危険です。「なんだか調子が悪いな」と感じた時は、無理せず専門業者に依頼してください。
4.掃除の際にファンを濡れたまま取り付ける

換気扇を掃除する際、ファンを取り外して水洗いする必要があります。しかしこの時、ファンを乾かす時間がもったいないと濡れた状態のままファンを取り付ける行為は絶対にやめてください。付着している水分が本体に入り込み、換気扇の故障を招く原因となるからです。
後ほど正しい掃除方法を紹介しますが、ファンやフィルターなどは、水洗いした後、乾拭きし、さらにしっかりと乾かしてから取り付けるようにしてください。
5.換気扇の電気回線コードを触る
換気扇を掃除する際、電気回線のコードを触ってしまったり、いじってしまう人がいますが、この行為もNGです。故障や接触不良を引き起こし、換気扇が正常に動かなくなるトラブルを引き起こすからです。掃除の際は触れないよう慎重に部品を取り外すようにしましょう。
換気扇の正しい掃除方法やお手入れ方法を解説

換気扇の寿命をなるべく長く延ばすためにも正しい掃除方法を覚えておきましょう。まずは換気扇のお手入れをするために準備するべきものをご紹介します。
- ゴム手袋
- 使い古したスポンジ
- 雑巾
- 中性洗剤
- 新聞紙
油汚れがファンにこびりついている場合、強力すぎるアルカリ性洗剤は換気扇を傷つけてしまう恐れがあるので、換気扇専用のアルカリ性洗剤を使用するようにしましょう。
換気扇の正しい掃除方法

- 電源を切ってコンセントを抜く
- 手袋をつけた状態でレンジフードや換気扇の蓋を開けてフィルターを取り外す
- カバーとファンを取り外す
- シンクなどを使用してフィルターやファンに中性洗剤をかけて数十分放置する
- 時間が経ったら使い古したスポンジで汚れをこすり落として水洗いする
- 乾いた雑巾で水気を拭き取り、新聞紙の上で乾かす
- 最後に布巾や雑巾で換気扇の周りを拭き、フィルターやファンを取り付けて完了
フィルターやファンを外す際、レンジフードによってはネジで固定されていることがあります。その場合はドライバーを使い、慎重に取り外すようにしましょう。
換気扇は半年に1回を目安に掃除すると安心♪

換気扇は放置していると汚れが溜まり、上手に換気できなくなります。半年に1回を目安に正しい掃除を実践し、常に効率よく換気ができる状態を保つようにしましょう。