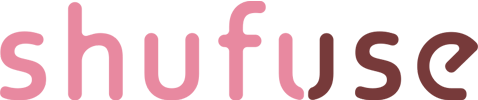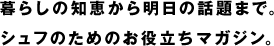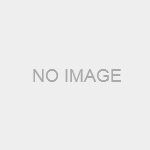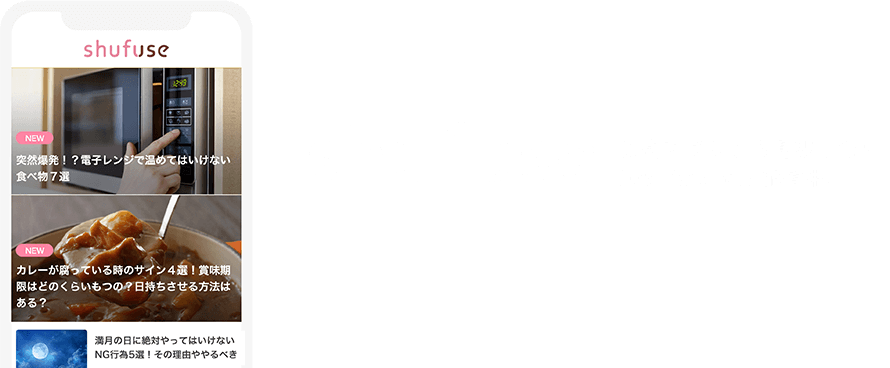目次
食後の眠気はなぜ起こる?考えられる3つの原因

1.血糖値の低下
食後に眠くなる原因のひとつは血糖値の低下です。食事をすることによって血糖値は急激に上がり、その後は徐々に下がります。血糖値が下がると血圧も下がるため心臓の働きが弱くなり脳への血流も減少し脳が働けなくなって眠気を引き起こすのです。
2.生き物本来の生存本能
弱肉強食の世界で生きる野生動物は、空腹を感じたら他の動物を襲わなければ生きられません。そのため空腹時には脳を覚醒させて感覚を研ぎ澄ませる物質「オレキシン」が活発になります。オキシンが活発なときは脳が覚醒していますが、活動が落ち着くと眠気を引き起こすと考えられています。この機能が人間にも備わっているため、食後に満腹になると眠くなるのではないかといわれています。
3.消化吸収を促している
食事のあと体の消化器官は食べ物を消化し、必要な栄養を吸収しようとします。この時に人の体は副交感神経が優位になり体をリラックスさせるのです。そのため食後は特に眠気を引き起こしやすいといわれています。
食後の眠気は糖尿病の初期症状?

食後の眠気は健康的な人でも起こるため、あくまでも生理的な現象だと考えて問題視しない人が多いでが、あまりにも眠気が強いときは糖尿病のサインかもしれません。
糖尿病は放っておくと腎不全や心臓病といった内臓疾患、アルツハイマー病や認知症といった脳の疾患につながる危険性もあります。あまりにも眠気が強い場合は医師の診断を受けることをおすすめします。
食後の眠気を防ぐには?

1.炭水化物を控えめに
糖分が含まれる炭水化物を控えめにしてみましょう。糖分の摂りすぎや急激な摂取が血糖値の乱高下につながり眠気を引き起こします。全く食べてはいけないわけではありませんが、丼物をさけたり、野菜もバランスよく食べられるメニューを選ぶといいでしょう。
2.食べ方を工夫する
食べる順番や食べ方を工夫するだけでも糖質の急激な摂取を抑えることができます。野菜や食物繊維の含まれる食材を先に食べると糖の吸収がゆるやかになります。また食べすぎも血糖値の急激な乱高下につながるので、食べすぎを控えるためにゆっくりと時間をかけて食べるのもおすすめです。
3.間食を活用する
血糖値の乱高下を防ぐために、間食を活用して糖分が一定量を保てるようにしてみましょう。こまめに間食することで一回の食事で食べすぎるのを防ぎ、食事による急激な血糖値の上昇を抑えることができます。
4.睡眠の質を上げる
睡眠不足が原因の眠気ということもあります。基本的には1日6時間以上の睡眠をとるのがベストです。また寝る1時間前にはスマートフォンやパソコンの画面を見るのをやめる、寝る前1~2時間は湯船に浸かるなどの工夫で寝つきがよくなり良質な睡眠が得られます。
食後に眠いと感じたら食生活の見直しを

食後に眠くなる原因は低血糖が大半ですが、あまりにも眠気がひどい場合は医師の診察を受けることをおすすめします。健康を保つためにも血糖値の急上昇を防ぐ食事を心がけましょう。