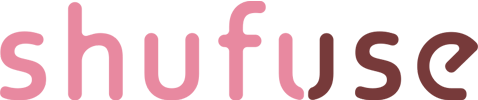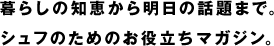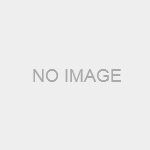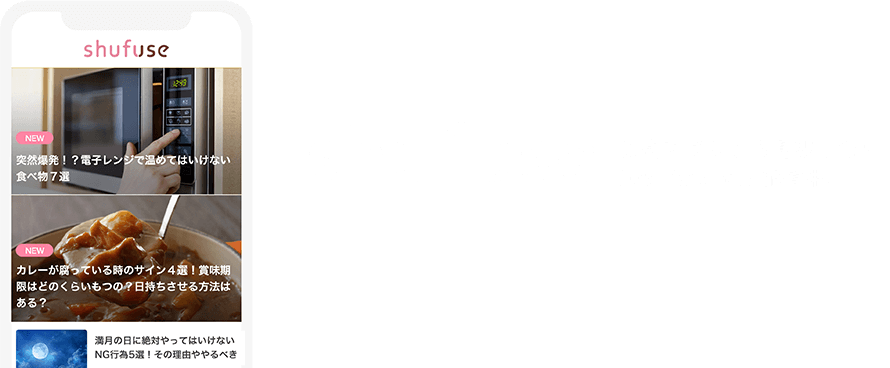目次
恵方巻きはいつから流行った?

恵方巻きが流行ったキッカケはセブンイレブンでの販売キャンペーンからでした。
- もともとは大阪の一部の風習だった
- 全国に広がる最初のきっかけはセブンイレブンでの販売
- 一気に全国に広まったのは1998年のセブンイレブンでの全国での販売キャンペーン
恵方巻きが流行ったキッカケは、広島県のとあるセブンイレブンの関西出身のオーナーのアイデアでした。『節分に太巻きをどうぞ』と、独自の販売促進活動で店頭販売してみたところ、大変好評だったそうです。その結果、セブンイレブンの他店、他エリアでの販売が始まりました。
その後、徐々に恵方巻きの販売が広まり全国で一斉にセブンイレブンが節分の日の恵方巻き販売キャンペーンを開始したのが1998年です。
ここから全国に一気に恵方巻きの存在が広がり、他コンビニチェーン、寿司チェーン店、デパートやスーパーのお惣菜コーナーなど、恵方巻きは全国的な風習となりました。
近年では節分当日、都内や近郊のデパ地下や、駅ビルのお総菜売り場やすしチェーン店で、予約済みの恵方巻きを受け取る人々の行列を見かけることもしばしばあります。
恵方巻きの由来

元々の恵方巻きの始まりは季節行事でも神事でもなかったそうです。
- 大阪の船場の花街が発祥地らしい
- そもそものはじまりは神事や伝統行事ではなく花街のお遊びだった
もともとは、大阪の船場の大店の旦那衆と妓女(ぎじょ)達の間ではじまったお遊びが発端だったと言われています。
それが少しずつ季節の行事となり市井に広まっていき、明治末期には大阪の一般家庭でも節分に恵方巻きを食べていたという記録があるそうです。
大阪で一般的になるきっかけになったのは、昭和の初期のころ『大阪鮓(すし)商組合後援会』が「幸運巻寿司」の販売促進用にビラを配布したとも言われています。
『この流行は花柳界ではじまりこの幸福巻きを恵方を向いて、無言で一気にまるかぶりして食べるとその年1年幸運に恵まれます。』という意味の内容がビラに書かれていたそうです。
現在、全国で広まっている恵方巻きの食べ方そのものです。
恵方巻の正しい食べ方

その年1年の幸運をしっかり授かるには恵方巻きの食べ方にルールがあるそうです。ずいぶん浸透してきたルールですが、もう一度あらためてチェックしましょう。
恵方を向いて食べる
その年の恵方(歳徳神という神様がいらっしゃる方向)を向いて食べます。よそ見することなく、食べている間はこの恵方だけを見ていることが大事だそうです。この恵方は毎年変わるのであらかじめ今年の恵方をチェックすることをお忘れなく。
ちなみに、2022年2月3日(木曜)の恵方巻きの方角は「北北西」です。スマホのコンパスアプリで方位角を確認すると「345°」になります。
恵方巻きはだまって食べる
食べ始めたら食べ終わるまで無言で食べます。途中のおしゃべりは厳禁です。おしゃべりは食べ終えるまで待ちましょう。
恵方巻きは一気に食べる
食べやすく切り分けてはいけません。一本丸ごと一気に食べます。途中で食べるのを止めるとご利益が減るそうです。
恵方から目を離さずおしゃべりせずにだまって一本丸ごとをいっきに食べきることがルールのようです。
恵方巻と太巻きの違い

恵方巻と太巻きの違いについてご紹介したいと思います。
太巻き
太巻き寿司には様々な種類のものがあります。
太目の巻物で酢飯を板海苔で巻き上げ、巻かれた酢飯の中心には様々な具材が入っています。ネギトロの太巻きもあれば、玉子焼きや煮付けたかんぴょう、きゅうり、魚のデンブの具材の甘めの太巻き、海鮮系の太巻きもありバラエティ豊かです。
カリフォルニアロールの太巻きなども最近ではよく見かけます。太巻き自体は酢飯を海苔で巻き上げて中に具材を入れること以外でルールなどは特になさそうです。
恵方巻き
恵方巻きにはちょっとしたルール、ゲン担ぎがあるようです。
中の具材を七福神に見立て、7種類を使うことになっているようです。具材に決まりはないようですが、煮付けたかんぴょう、煮付けたしいたけ、だて巻き、うなぎ、きゅうり、おぼろ(またはでんぶ)が使わるのが一般的だったようです。
近年では豪華な海鮮であったり、とんかつやスイーツなどバラエティ豊かです。
最後に

恵方巻きはセブンイレブンのキャンペーンがキッカケで全国に流行したのは意外でした。もとは大阪の花街が発祥地で大阪の市井へ、そしてさらに関西から全国へと広まりました。
近年では様々な具材の恵方巻きが店頭に並び、選ぶ楽しみにもなっています。次の節分には自分好みの七種の恵方巻きを探してぜひ購入したいと思います。