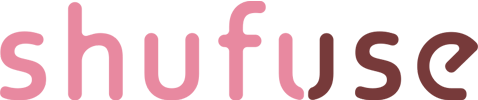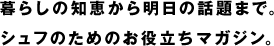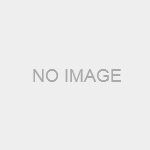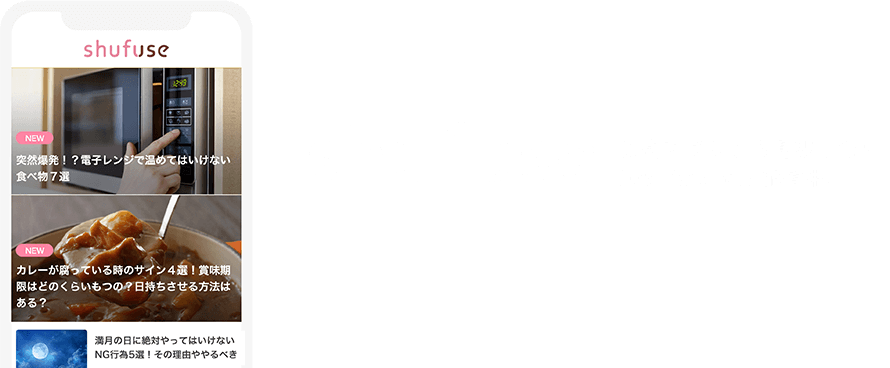目次
『お焼香』は仏様を讃えるために浄土を表現した供養法

お世話になった方やご家族のお葬式には、必ずお焼香の場が設けられます。そもそも『焼香』は、仏教において香を焚くというという意味の言葉です。仏教が日本に伝わったと同時に、焼香の文化も伝わったと伝えられています。
仏教では、香を焚くことで仏様が住む浄土を再現しています。仏様が住む浄土は、独特な良い香りを含んだそよ風が、あたりに漂っていると考えられているため、その浄土を表現するために焼香が行われます。
焼香を行うことで、香りが全ての人に行き渡ることから、仏様の慈悲を全ての人が受けることができ、仏様への賛辞を讃えることになると考えられています。そのため、仏教式のお葬式では、必ず焼香が行われるのです。
お焼香は宗派によって回数や方法が異なる
すでにお葬式に参列する機会が何度もあるという方は多いでしょう。その際、お焼香で悩むのが宗派ではないでしょうか。お焼香は、宗派によって香をつまみ、額に押し戴く回数が異なるからです。
「故人は仏教の中でもどこの宗派だったのだろうか」「何回行えばいいのだろう」と悩む人は、ご自身の宗派に合わせた回数を目安に行うと良いでしょう。1〜3回、額に押し戴く方法が一般的です。
基本的なお焼香のやり方は?手順を解説

ここでは基本的なお焼香のやり方を確認していきましょう。今まで「なんとなく目の前の人の真似をしていた」という方は、改めて正しいお焼香のマナーを確認してください。
- 焼香台の少し手前で遺族と僧侶に一礼する
- 焼香台の前へ進み、遺影に一礼する
- 数珠を左手にかけ、右手でお香をつまみ、額に押し戴く
- お香を香炉の炭の上にくべて合掌する
- 焼香台から少し下がり遺族に一礼して席に戻る
この方法が基本的なお焼香の手順となります。しかし、先にもお話しした通り、故人の宗派によってお香を押し戴く回数が異なったり、中にはお香を額へと掲げないケースもあります。
神道式の場合は、お焼香ではなく玉串奉奠(たまぐしほうでん)となるので、玉串を時計回しに回して左右持ち帰るなどの作法が必要となります。
遺族の場合は弔問客への一礼を忘れずに

先に紹介したお焼香のマナーは、弔問客としてお焼香する場合です。故人の遺族の場合は、遺族に一礼するのではなく、お葬式に参列してくださった弔問客の皆様に一礼しましょう。
大人の正しいマナーとして数珠は用意しておこう

お葬式に参列する際、「絶対に数珠は必要なの?」と思う方もいるかもしれません。大人のマナーとして、お葬式に参列する際は、必ず数珠を持っていきましょう。
数珠は本来、お葬式において魔除けや厄除けの意味合いがあります。そのため、「今日は数珠を持ち合わせていないから」と他の人から借りようとするのはご法度です。必ず事前に自ら用意した数珠を持っていきましょう。
宗派によってお焼香の回数が違う?行う順番は?

先ほどから幾度となく宗派によってお焼香の回数が異なるという話が登場しています。では、具体的に宗派によってどの程度、お焼香で香を額に押し戴く回数が異なるのでしょうか。
宗派別のお焼香の回数
宗派別のお焼香の回数は以下の通りです。
- 天台宗、浄土宗、日蓮宗…香を1〜3回額に押し戴く
- 真言宗…香を3回額に押し戴く
- 臨済宗…香を1回額に押し戴く
- 曹洞宗…1回目は香を額に押し戴く。その後、2回は額に掲げずそのまま香炉へくべる
- 浄土真宗…額に掲げず、香をそのまま香炉にくべる
以上が宗派ごとのお焼香の回数に関するマナーです。お寺でお葬式を行う場合は、お寺の宗派を事前に調べるとわかります。しかし、最近ではセレモニーホールなどで執り行うご家庭が多いので、故人がどの宗派であるかは見当がつかないことが多いです。
したがって、ご自身の宗派の作法でお焼香を行いましょう。また、葬儀が執り行われる場所によっては、立礼焼香と座礼焼香、場合によっては回し焼香が行われるケースもあります。こちらは臨機応変に対応していきましょう。
お焼香を行う順番は関係が深い順に
皆さんはお焼香を行う順番が気になったことはありますか。一般的に、お焼香は関係が深い順に行われます。したがって、最初に喪主がお焼香を行い、それに続いて遺族が、そして親族、弔問客と続いていきます。
最近は、葬式場の座席が決められているケースも多いです。その場合は、座席に従って順番にお焼香を行いましょう。2〜3人で同時にお焼香を行う場合は、一緒に焼香台へ立った人同士、一緒に立ち去るのが一般的です。
大人の礼儀作法としてお焼香マナーを知っておこう

いかがでしたでしょうか。お葬式において、最も悩む作法がお焼香という方は意外と多いです。今回紹介した基本のやり方や作法を事前に知っておくことで、当日慌てず落ち着いて故人をお見送りすることができるはずです。