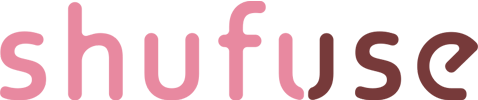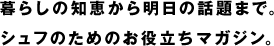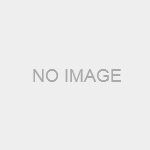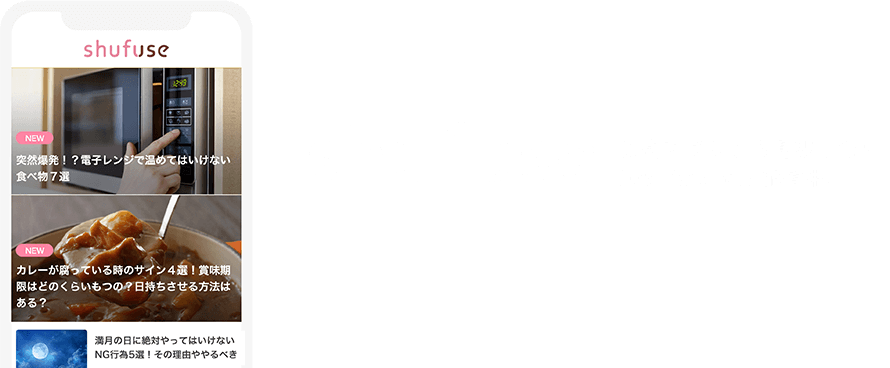目次
使うべきではない『まな板』6選!
1.食材の種類ごとに使い分けしていない『まな板』

まな板は「これから加熱する肉や魚用」「野菜や調理済みの食品用」と2~3枚を使い分けるのがおすすめです。
生肉を切ったまな板には肉の表面についている菌が付着しています。洗剤で洗ったとしても、加熱調理をしない生野菜や刺身などは別のまな板を使ったほうが安心です。
もし使い分けをしないで同じまな板を使う場合は、まな板だけでなく包丁もよく洗ってから切るようにします。または、野菜などの食材から切り始め、次に肉類や調理する魚を切るなど工夫しましょう。まな板を使い分けることや切る順番によって食中毒を予防することができます。
2.乾いたまま水で濡らさない木製の『まな板』

乾いている木製まな板はそのまま使うと汚れが付着しやすくなるそうです。木製まな板は包丁が傷みにくいなどのメリットもありますが、表面に傷がつきやすいというデメリットもあります。キズが付いていると雑菌が入り込みやすく、カビや黒ずみの原因となります。
そこで、使う前にまな板を水でぬらすことで、木の奥まで汚れや食材のにおいが付きにくくなるそうです。水をかけて濡らした後は、キッチンペーパーや清潔な布巾で水分をきちんとふき取ってから使ってください。
3.抗菌剤『まな板』も水で濡らさないのはNG

抗菌剤配合の樹脂製まな板なども、木のまな板と同じく使う前に水を浸け布巾などでふき取るようにしましょう。抗菌剤の効果は、使われている銀イオンが水にぬれることで雑菌の発生を抑える効果を持っているそうです。
そのため、濡らさずに乾燥した状態で使うと抗菌の効果がほぼ期待できないそうです。水をかけて濡らした後は、キッチンペーパーなどで水気はふき取りましょう。
4.肉・魚・卵を切った『まな板』に熱湯はNG

生肉を切ったまな板には菌が付着しているため、除菌をすると安心です。手軽にできる殺菌方法は熱湯をかける除菌です。ところが、生の肉を切った直後に熱湯をかけると付着している肉のたんぱく質が固まってしまいかえって汚れが落としにくくなるそうです。
たんぱく質は約58℃を超えると凝固する性質があるためだそうです。生肉だけでなく魚や卵などたんぱく質を含む食材も同じです。これらの食材は、熱湯ではなく水と洗剤で洗ってから、除菌が必要な場合は熱湯除菌をしましょう。
5.使いこんでいる古い『まな板』

古いまな板をずっと使っていると、表面に雑菌が付きやすくなっています。まな板にできた細かな傷は汚れが入りやすく、なかなか落とせません。
キレイになったように見えても少しずつ溜まった汚れから雑菌が繁殖しているそうです。使いこんでいる古いまな板をいつまでも使うのはやめましょう。
6.歪みや反りが発生した『まな板』

プラスチック製やゴム製のまな板は熱に弱く、焼きたての料理を切ったり食洗器に入れてしまうと歪みや反りが発生しやすいです。多少歪んでいたり反りがあっても汚れていないから使っている、という方もいるかもしれません。
ですが、歪んだまな板や反りのあるまな板は使用しにくく、包丁を使う際にけがをする可能性も高いです。歪みや反りが発生したら、汚れていなくても交換するようにしましょう。
さいごに
まな板は使った後にしっかり洗っていてもキズの中の汚れは蓄積し、雑菌が繁殖しやすくなります。使った後の汚れは洗剤でよく落とし、すすぎも徹底しましょう。
洗剤が残っているとカビが発生しやすくなるそうです。また、大切なポイントは洗ったまな板は水気をふき取りよく乾燥させることです。そして、必ず風通しの良い乾燥している場所で保管して下さい。